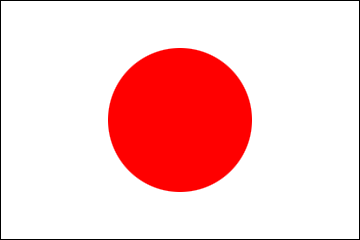海外在住が及ぼす精神的な影響
目次
- はじめに
- 人間は変化を望まない
- 変化によって「失ってしまうもの」「無くなるもの」
- 変化に伴う人間の反応
- 海外移住と心の動き
- それぞれの状況について(駐在員、その家族、学生)
- 今の自分を感じること
- 何をすればいいのか
はじめに
海外での生活は負担が大きく、精神的に不安定になりやすいことは、多くの人が多かれ少なかれ、経験しています。しかし、何故そんなに負担を大きく感じるのかについては、余り深く考えられていないと思います。この問題に注意を向けることで、自分自身の心の状態に目が向き、結果的に精神的な安定、ひいては長期に渡って落ち込むことを防ぐことにつながり、また、落ち込んだとしても、症状の緩和につながることが考えられます。私は、ロンドンにおいて心の問題を抱えるようになられた日本人の方々の治療に、10年以上携わってきました。毎月5~10名の方が、精神的な悩みを抱えられて、新たに診察に来られます。そうした経験を元に、何が負担であるのかを少し細かく考えていきたいと思います。
人間は変化を望まない
個々の差はありますが、人間には本来、様々な変化を余り望まない部分があります。ある意味、発達を望む気持ちと、何も変化しない状態を願う気持ちとの間の葛藤が、多かれ少なかれ起こっているのです。年齢が上がればその傾向は、強くなっていきます。
これまで住んでいた国を離れることは、たとえ本人が望むものであっても、心に大きな変化を及ぼします。変化することは、必ず「何かを失うこと」につながることになるのです。それでは「何を失う」ことになるのでしょうか。
変化によって「失ってしまうもの」「無くなるもの」
海外生活で変化するものとして、(1)言葉、(2)文化・習慣、(3)自分の周りにいる人々、(4)生活環境、など、多くのものがあります。
- (1)言葉
自分の要求を相手に伝えたり、交渉したり、自分の気持ちを言葉にしたりなど、日本ではごく普通にできていたことが、言葉が変わることで、急にできにくくなってしまいます。日本語では出来ていたことが、出来ないという、不満感や失望感を感じることにつながります。 - (2)文化・習慣
日本では余り考えることなく、当たり前であると思っていたことが、相手に全く通じなかったり、相手が何も気にしていないという経験に、繰り返し出くわすことも希ではありません。 - (3)自分の周りにいる人々
これまで馴染みのなかったような人たちに囲まれて、頭の中ではわかっていても、恐怖感、違和感を感じることがあります。さらに大切なこととして、自分のことを比較的自由に話すことができた人、一緒に何かを共有してきた人たちが、身近に少なくなっていることが多いでしょう。 - (4)生活環境
趣味など、「これをしていれば時間を忘れられる」ということが、できない環境にいる方も多いと思います。
変化に伴う人間の反応
こうした変化には、かなりの部分で共通している点があります。その一つは、これまで自分が、普通にできていたこと、安心だと思っていたこと、安全であると感じていたことが、「無くなってしまう」ことです。 例えば、自分で考え、判断し、責任を持って行動できていた自分が、英国に来たことで、そうした行動を取ることが突然難しくなり、自分が無力な状態に陥ってしまったと感じることがあげられます。 さらに、これまで自分自身の生活に潤いを与えてくれたり、充実感をもたらしてくれたりしていたものも、「無くなって」しまっていることもあります。以上のような状態に置かれると、人間は次のような反応を示しがちです。
- (1)普段はそれほど衝撃を受けたり、深く影響を受けたりしない事柄に、容易に動揺してしまったり、傷ついてしまう。
- (2)些細なことでも、自分が責められたり、非難されているように感じ、それにより逆に相手を責めたり、非難してしまう。こうして、気づかないうちに自分を守ろうとしてしまうかもしれません。(これは家族間でも起こりえます。)
- (3)その結果、自分の変化に動揺し、落ち込んでしまう。
海外移住と心の動き
海外への移住で及ぼされる大きな変化と、それに伴う心への影響は、日本での毎日の生活において普通に行えていたことが、急に「無くなってしまう」ことに拠っている部分が大きいと考えられます。このことは当然のことであると、思われる方もいるでしょう。しかしながら、「多くの人たちが、喪失が及ぼす気持ちへの影響を意識していない」という経験を、ロンドンでの診療の中で、間近に感じてきました。それは多くの場合、次のような過程を経ています。
- (1)「失ったもの」を感じることは、深い悲しみ、大きな痛みを伴う。
- (2)「何を失ったのか」が実感できず、「失った」という経験を認められない。
- (3)「無いもの」、「いない人々」にばかり目が向いてしまい嘆き続ける。
- (4)今目の前にある、大切なものに、目を向けていくことができなくなる。
日々の診察では、以上のようなどうにもならない思いの中で、落ち込んでいってしまった方々を数多く診てきました。
それぞれの状況について(駐在員、その家族、学生)
次にそれぞれの方々の置かれた個別の状況について、少し考えてみたいと思います。診察に来られる方々の多くは、大きく3つのグループに分けることができます。(1)企業からの派遣で駐在員として来ている方、(2)その家族、(3)そして学生の方です。 この3つのグループの方々が置かれやすい状況と難しさについて、少し考えてみたいと思います。
- (1)企業駐在員の方
英国に派遣されたのが、本人の希望によるものかどうかというのは、大きな要素です。本人の希望である場合、多くの方は強い期待を持っており、そこから来るプレッシャーは大きくなります。もし実際にこちらで働き始めて、自分の思い描いていた姿との落差が大きかった場合、また、何年も働いてきた前任者のように働けないと感じた場合、その期待、プレッシャーが心を押し潰すように働くこともあります。期待に応えようとするが故に、もしくは、期待に応えられなかったときに、自分が自分に対してどう思うのかという不安のために、休みもなく働くようになっていった方々が数多くいました。逆に、本人が希望していなかったときは、何故自分が、(これまで述べてきたような)精神的に辛い経験をしないといけないのかと、会社に落胆したり、会社を恨んだりすることがあります。これらは、働く意欲を削いでしまいます。加えて、英国においては、多くの場合、事務所の規模が小さく職場の人間関係が心に大きく影響します。人間関係においては、必ず得手不得手があります。こういう人は自分には合うけど、こういう人は苦手という感覚です。関係が上手くいかないと、理解されない悲しみや怒り、不当に扱われていると感じることから来る不信感や怒りなどの気持ちに覆われやすくなります。その結果、周りの人々や自分に対しての信頼感が揺らぎます。日本では事務所の規模が大きいことが多く、上司と部下の間の差異から生じる思いや気持ちは、いろいろなタイプの人がいるため、他の人との関係で気持ちを処理しやすいと思われます。同時に、日本においては、会社の外での関係や活動が、失われた信頼感、安心感を取り戻す助けになっています。海外への赴任では、それらは「無なくなって」しまいやすくなります。 - (2)駐在員で派遣された方の家族
ここでは、主に駐在員の配偶者の方々が多く経験されることについて触れたいと思います。多くの場合、英国での生活は本人(配偶者)の希望ではないでしょう。これまで働いてきた会社、これまで時間をかけて培ってきた人との関係や活動を、英国に来るということで、捨てざるを得なかった方が大半だと思われます。そのため自分が「無くした」ものの大きさに打ち拉がれることになります。加えて、駐在員本人も自分の置かれている状況に精一杯になってしまい、配偶者の心の状態にほとんど目が向かなくなることが少なくありません。そのため、配偶者の孤立感がより強くなることとなります。その結果、自分の中で湧き起こってくる強い気持ちに圧倒され、孤立感と共に落ち込んでしまったりする方が多くいます。 - (3)学生の方
英語学校に来ているのか、大学、もしくは大学院での勉強を目的で来ているのかで、状況は少し異なるでしょう。 大学院や大学での勉強が目的の場合は、英語という言葉の壁ばかりでなく、実際の授業の進められ方、また、議論に対する態度などに圧倒されることが多いと思われます。英国ではディスカッションに重きが置かれます。特に自分がテキストや講義から何を学び、何を疑問に思ったのかを、どう話し合っていくのかが、学ぶことの大切なプロセスと捉えられています。知識を獲得することが主な目的である日本の教育とは大きな差があります。英語に対しての気後ればかりでなく、そうした差異も大きく気持ちに影響するでしょう。そのため、周りから遅れてしまっている、一人だけ取り残されているという感覚を持ちやすくなります。また、長期の休みが多い反面、学期中のカリキュラムは厳しく、多くの場合、膨大な量の文献を読まなければいけなかったり、課題をこなさなければいけなかったりします。そのため自分の時間を取ることが難しくなり、余計に孤立感を感じることになります。 英語学校に英語の取得のために来ている学生の方は、自分の英語がなかなか上達しないことに苛立つことも多いようです。英国やアメリカに住んでいれば、3ヶ月で今まで聞こえなかった英語がわかるようになり、半年、1年もすれば、自由に英語でコミュニケーションが取れるようになる、という話しを耳にすることがあります。最近はさすがに減ってきているようですが、未だにそれを信じている方も多いように思います。成人してからの新しい言語の獲得は、とにかく長い時間と大変な労力を要するものです。地下鉄やバスで日常の会話が他人とできるようになるのには、何年にもわたり英語環境での生活をすることが必要だと言われています。それほど大変な作業です。そのことを理解しないまま、自分は出来ないと思い込み続け、落ち込む方も少なくありません。
今の自分を感じること
ここまでは、いかに海外での生活が、人々の心に大きな影響を及ぼすのかについて考えてきました。自分がこれまで当然だと思っていたものを、「失うこと」から生じる様々な思いや自分自身に対しての過剰な期待から来る複雑な気持ちが、いかに大きく関わっているのかが、お分かり頂けたかと思います。自分が「失ったもの」、「無くなったもの」を実感できない限り、自分が何を求めているのかを感じることはできません。自分がいかに過剰な期待を自分に課しているのかを感じられない限り、自分が今行っていることに価値を見出せなくなります。同時に、こうした状況に陥ると、人は孤立しやすくなるものです。人は、孤立感、不全感、不安感を感じると、周りへの不信感、失望感などに敏感になり、その結果、孤立感に拍車をかけやすくなります。診察室の中で、「話してみたら、自分が思っていたより周りの人がわかってくれて、ほっとした」という言葉を何回も聞いてきました。
何をすればいいのか
最後にもう一度目を向けて頂きたいことがあります。海外で、言葉も自由に使えない、慣習も考え方も違う、これまで馴染みのない人で溢れた場所で生活することは、とにかく大変であるということです。そのことを繰り返し自分に語りかけていくことが、とても大切なことです。また、目を自分の外に向ければ、今まで得られなかった新たな機会や新しいものの見方が溢れています。それでも、気分が落ち込んだり、感情の起伏が激しくなり、加えて、不安で眠れず、食欲もなく、考えが全くまとまらず、自分には何も価値がないと、感じるようになったら、専門家に相談して見て下さい。相談したいと思われれば、いくつかの方法があります。ひとつは、地元のGPに相談することです。薬物療法、カウンセリング、精神療法などNHS(国民健康保健サービス)での様々な形の治療法について、話し合うことができます。また、日本語で相談できる団体もあります。日系の医療機関もそのひとつです。余り一人で抱え込まず、専門家に相談されることを勧めます。
在英国日本国大使館 精神科顧問医
阿比野 宏